「無添加」「添加物不使用」が使えなくなる!?食品表示ガイドラインを深掘りしてみた
この記事は2022年5月1日にポッドキャストで話した内容を要約したものです。
2022年3月に食品のパッケージに“無添加”“添加物不使用”という表示ができなくなる!?という話題について、加工食品メーカーで表示作成を担当していた私が、ガイドラインを読んで深掘りしてみました。
実は悪用されている場合も・・・
添加物を避けるためにはどうすればいいのか?
大手メーカーのための法改正なのか?
目指すべきは鉄腕DASH??
記事の概要
「無添加」「添加物不使用」といった表記が使えなくなる――そんなニュースが話題になりました。この記事では、実際に加工食品の表示を担当していた立場から、食品添加物の不使用表示に関するガイドラインを読み解きます。
「無添加」と書けなくなる理由
2022年3月16日、食の安心・安全をつくる議員連盟と消費者庁が意見交換を行い、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が策定されました。これにより、今後は次のような表示が厳しく制限されます:
- 保存料不使用などと書いても、同様の効果がある物質を使っていればNG
- 原料の原料に添加物が含まれていれば「不使用」とは言えない
- 他社を誤解させるような「○○不使用」も禁止
表示の“抜け道”とは?
某パンメーカーの「保存料不使用」商品には実はクエン酸が使用されていました。クエン酸は酸味料にも保存料にもなり得ます。法律上は問題なくても、実質的には保存目的の添加物として機能していたケースです。これがガイドラインで防ぎたい「有利誤認」表示です。
「キャリーオーバー」「加工助剤」も対象に
キャリーオーバー(原料由来の添加物)や加工助剤(工程中に消える添加物)も含まれている場合は「無添加」とは表示できません。原料の原料までトレースが必要で、個人商店には非常にハードルが高い規定です。
大手・個人商店・農家への影響
このルールにより、大手メーカーでも「無添加」表示はほぼ不可能。個人商店では追跡調査が難しく、最も恩恵を受けるのは自ら農産物から加工まで手がける農家です。つまり、本当の意味での無添加は“自家製”だけ。
消費者にとって大切な視点
「無添加表示が消える=不安」ではなく、むしろ誠実な表示を守るための一歩です。信頼できる生産者から買う、裏面表示を読む。これが新しい“食のリテラシー”です。
まとめ
この改正は大手を守るためではなく、抜け道商法を防ぐためのルール。結果的に、正直にものづくりをする人たちに追い風となるはずです。
無添加を本気で目指すなら、自分で作るしかない。つまり鉄腕DASHの世界です。
この記事は2022年5月1日にポッドキャストで話した内容を要約したものです。


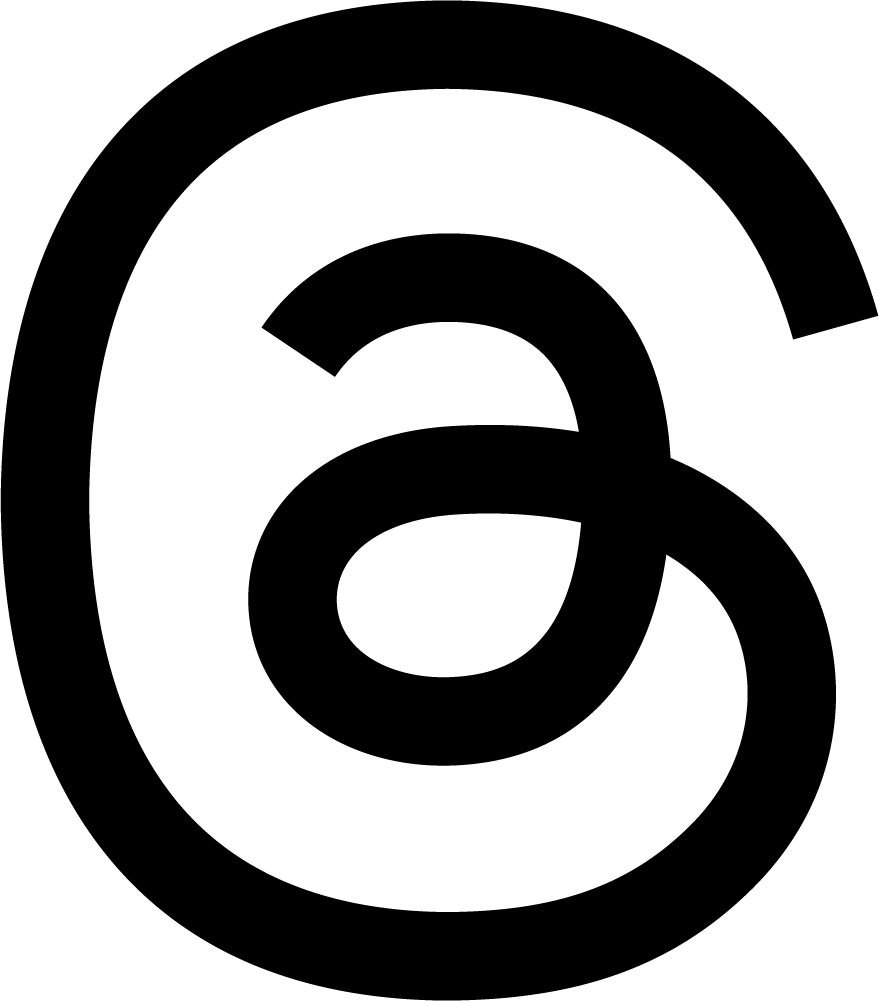 Threadsはこちら
Threadsはこちら