農薬について思うこと ― 有機農業と安全性のはざまで
今日は「農薬」について、日頃感じていることをお話ししたいと思います。
「農薬」と聞くと拒否反応を示す方も多いかもしれませんが、そもそも農薬とは何なのでしょうか。
農薬とは何か?
農薬とは、農作物を害虫や病気から守るために使われる資材の総称です。
一般的に「化学的な薬品」と思われがちですが、実際には 生物由来の農薬 もあります。
例えば、テントウムシも農薬として登録されています。
アブラムシを食べて害虫の発生を抑えるためです。
実際には、飛ばないように品種改良されたテントウムシも販売されており、これも立派な「生物農薬」です。
有機農業で使える農薬
「有機農業=無農薬」と思われがちですが、実際には有機JASで使用が認められている農薬があります。
主なものは以下の通りです。
- マシン油(油剤):昆虫の体表を覆い窒息させる。
- ボルドー液:植物表面をコーティングし病原菌の侵入を防ぐ。
- BT剤(バチルス・チューリンゲンシス):虫が摂取すると腸内で働き、殺虫効果を示す微生物。
これらは神経毒のような化学的な殺虫作用ではなく、物理的・生物的な仕組みで害虫を防ぐタイプです。
民間農薬(牛乳・焼酎など)の実際
家庭菜園などで「牛乳スプレー」「焼酎スプレー」などが話題になりますが、
私の考えではどちらも殺虫効果は限定的だと思います。
- 牛乳 → 水分が多く、昆虫表面から流れ落ちてしまう。
- 焼酎 → 表面の油脂を落とすが、殺虫作用までは弱い。
植物のワックス層まで落としてしまうリスクもあるため、使用には注意が必要です。
化学農薬の安全性 ― 私の考え
科学的には「安全性が確認されている」とされていますが、
実際には長期的な人体への影響はまだ不明です。
農薬が一般的に使われ始めてから、まだ100年も経っていません。
つまり、今の私たちは「壮大な社会実験の途中」にいるのかもしれません。
とはいえ、農薬の恩恵も確かにあります。
食中毒を防ぎ、安定した収穫をもたらしてきたのも農薬の力です。
「農薬のリスクを恐れるよりも、万が一に備えて代替手段を用意する」
― それが現実的なスタンスだと私は思っています。
農薬のメリットとデメリット
メリット
- 病害虫やカビの発生を防ぎ、安定した収穫ができる
- フードロスの削減に貢献
- 安全基準のもとで使用されており、摂取量が管理されている
デメリット
- 人体への長期的影響は未知数
- 誤った希釈や散布で残留農薬のリスク
- 害虫の耐性化(抵抗性)問題
農薬の正しい使い方と現場の工夫
農家は正確な希釈・登録作物・使用回数・風向きなど、細心の注意を払っています。
特に「ドリフト(飛散)」対策としては以下のような工夫があります。
- 風速1〜2m以下での散布
- 静電気ノズルによる付着効率の向上
- 隣接作物との距離確保(2m以上)
- トレーサビリティ(使用履歴の記録・提出)
これからの農業に向けて
農薬は悪ではありません。
しかし、「使わなくてもできる技術」を追求することが、
これからの持続可能な農業にとって重要だと思っています。
有機農業・天敵農法・微生物農法など、
科学と自然を両立させる新しい農業の形を模索していきたいと思います。
まとめ(要約)
- 農薬には化学合成だけでなく、生物由来のものもある。
- 有機農業でも使える農薬(マシン油・ボルドー液・BT剤など)が存在する。
- 化学農薬の安全性は「現時点では安全」とされているが、長期影響は不明。
- 農家は散布時期・風向き・希釈率などを厳守して使用している。
- 今後は「農薬に頼らない技術」の確立が求められている。
農薬の進化と共に、私たちも「どう付き合うか」を進化させていく時期にあるのかもしれません。


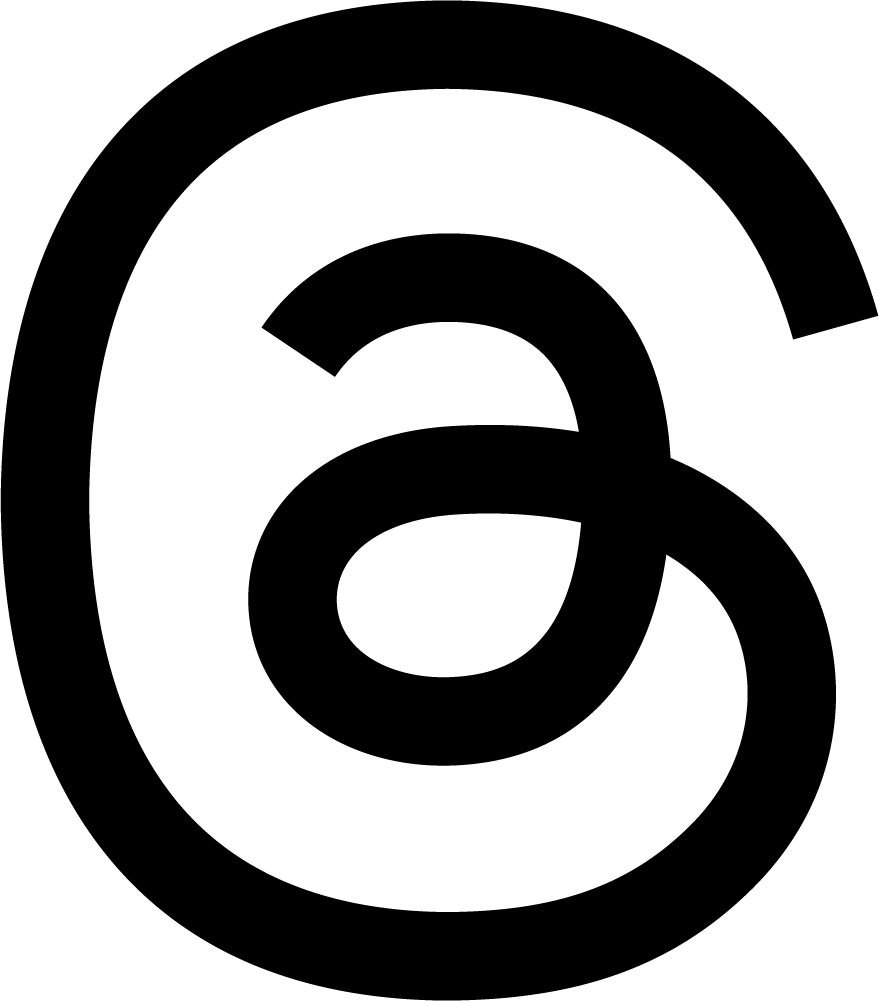 Threadsはこちら
Threadsはこちら