5歩目
新規就農、僕は100万円で始めました。
~群馬県館林市でゼロから農業ライフを築いたリアル~
群馬県館林市で2021年3月に新規就農した私が、どんな農家ライフを送っているのか、その実体験を赤裸々に語っているラジオ番組(ぱくぱく農園Podcast)を要約したものです。
【体験記】福島県沖地震で学んだ「備え」と、Podcast Weekendの交流
2022年3月16日23時36分、福島県沖で震度6強の地震が発生しました。私の地域では震度4を観測。幸い被害はありませんでしたが、停電と通信障害により「情報がない恐怖」を強く感じました。この記事では、地震から学んだ備えの大切さと、下北沢で開催されたPodcast Weekendの参加体験をまとめます。
福島県沖で震度6強の地震発生
深夜の地震発生直後、私の地域では停電が起き、真っ暗な中で家の揺れる音と地響きだけが響いていました。電波は届いているのにインターネットに繋がらず、情報が得られない不安と孤独感を実感しました。
東日本大震災を思い起こさせる記憶
今回の揺れは、2011年3月11日の東日本大震災を思い出させました。あの時は電気・ガソリン・食料が不足し、インフラ麻痺が長期間続いた経験があります。11年経った今でも、社会インフラの脆さは消えていないと痛感します。
突然のインフラ停止と食料問題
大雪や災害などで物流が止まると、日常の買い物すら困難になります。過去には、群馬県で大雪が降った際、スーパーに入るのに1時間待ち、入店しても商品がほとんど棚にない状況に直面しました。さらに、レジも人手不足で2台しか動いておらず、買い物を終えるまでに半日かかった経験もあります。
- 大雪 → スーパーに商品がなく、買い出しに半日かかる
- 戦争・経済制裁 → 小麦や石油、天然ガスの供給リスク
- 農業 → 天然ガス由来の窒素肥料が止まれば収穫量に直結
こうした要因は、日常生活に直結する大きな問題です。
有事に備えるためにできること
1. 備蓄
最低1か月分の食料備蓄を推奨。ただし、地震で家が倒壊すれば備蓄品にアクセスできない可能性も考慮が必要です。
2. 地域の生産者とつながる
自転車で行ける距離の生産者と関係を作っておくと安心。相互に補完し合える体制は、有事の際に大きな力となります。
3. エネルギーの自立
太陽光発電やソーラーシェアリングなど、自分で電気を作る仕組みを取り入れることが重要です。特に停電時にはスマホの充電・情報収集に直結します。
下北沢「Podcast Weekend」に参加して
3月12日、下北沢で開催されたPodcast Weekendに参加しました。ポッドキャスターとリスナーが直接交流できるイベントで、会場はお祭りのような雰囲気でした。
プレゼントで溢れる空間
来場者は「喜んでもらえる情報」や「体験」をプレゼントとして持ち寄り、とても温かい空気に包まれていました。
印象に残った交流
「ゆる言語学ラジオ」のサイン会に参加し、直接お話できたのは大きな喜びでした。また「農系ポッドキャスト共同組合」のブースでも交流でき、ポッドキャストの広がりを肌で感じました。
まとめ
- 地震から「情報遮断の恐怖」と「備えの大切さ」を再認識
- Podcast Weekendで「人と人のつながり」の温かさを実感
天災や社会情勢の変化は予測できませんが、日頃の備えと人とのつながりを意識することで安心感は大きく高まります。


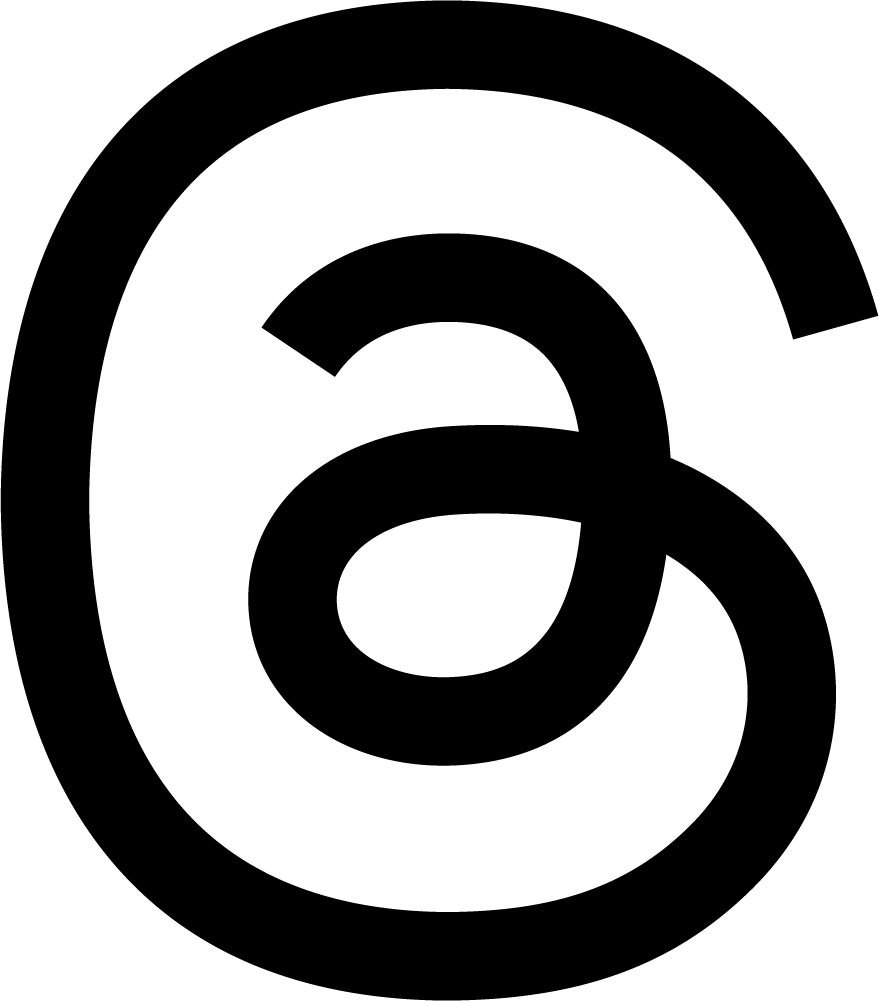 Threadsはこちら
Threadsはこちら